あなたは最近、じっくりと「考える」時間を持っていますか?
先日、友人がこんな話をしてくれました。彼の子供が通う進学塾の先生が言うには、今の10代から30代半ばの人たちは、「考える能力」が低い傾向にあるというのです。この話を聞いて、私自身の過去の経験と、日本の教育がもたらす影響について、深く考えさせられました。
この記事では、「考えること」がいかに私たちの人生にとって重要であるか、そしてなぜ多くの人が「思考停止」に陥ってしまうのか、その根本的な原因と対策を、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。
なぜ「わからない」という人が増えているのか?
私がこの仕事を始める前、SNSで相談に乗っていた時期がありました。相談者の中には、私の考え方やアドバイスをまとめたブログを「読んでみてください」と伝えても、「わからない」と返してくる人が少なからずいました。
確かに、私の文章が稚拙だったり、人生経験を積まないと理解しにくい内容だったりしたのかもしれません。しかし、もう一つの共通点があったのです。
それは、こちらから「読んでもらえましたか?」と聞くまで、「わからない」という返事すらしてこないこと。そして、返事がやたらと早いことでした。
最初は「面倒だから読んでいないのだろう」と思っていました。しかし、やり取りを続けるうちに、内容は理解していることがわかりました。つまり、彼らはブログを読んではいるのです。
そこで思い出したのが、冒頭で触れた塾の先生の話です。この「思考停止」の傾向は、特定の世代に顕著に現れているように感じました。
「思考時間」のない世代
私がアドバイスをしても、彼らは「良い」「悪い」の判断をせず、次の話題に移るか、同じ質問を繰り返すだけでした。小学生や中学生からの相談も受けていましたが、彼らは「わからない」と感じたら、わからないなりに自分の意見を述べてくれました。
一方で、大人になってからの相談者の中には、「わかる」か「わからない」の二種類の答えしか持ち合わせていない人が多いのです。
「わかればOK」 「わからなくてもそれで終わり」
この単純な思考回路は、返事の速さにも表れていました。彼らは「考える時間」を持たずに、反射的に反応しているだけなのです。
「考える」ことの本当の意味
「考えすぎるからいけないんだ」と悩んでいる人に言う人がいますが、それは思考が堂々巡りになって、身動きが取れなくなっている状態のことです。この場合は、一度思考をストップさせることも一つの手かもしれません。
しかし、ほとんどの人はそれができません。目の前にある悩みや問題を「考えないようにする」のは、非常に難しいことです。
答えのないことを延々と考えるのは不毛に思えるかもしれません。しかし、俗にいう**「欲を捨てると言う欲を持つ」**という言葉のように、「考えるのをやめる」ことすら、人は考えてしまうものです。
レイキヒーラーとして瞑想の仕方を尋ねられた際、多くの人が「無我の境地」を**「何も考えないこと」**だと勘違いしています。そして、「何も考えないように」と一生懸命考えながら瞑想しているのです。
人の心は、「考える」ことをやめてマニュアル的に反応していると、鬱になると言われています。
以前のブログでも書きましたが、外部からの情報を鵜呑みにするのではなく、**「確認する」**ことが重要です。その「確認する」という作業こそが、「考える」ことなのです。
情報はすべて、自分の外からやってきます。その情報を自分の頭で考えることで、初めて「自分のもの」になるのです。だからこそ、「考える」という能力は、生きていく上で非常に重要になってくるのです。
なぜ日本の教育は「考える力」を奪うのか?
ここで一つ、質問です。
「東京-大阪間を新幹線が走る間に車内販売でコーヒーは何杯売れるでしょう?」
これは雑学クイズではありません。大手企業の面接で、実際に聞かれることがある質問です。
この質問の意図は、「正しい答え」を知っているかではなく、面接官を納得させられる**「推論」**を組み立てる力があるかを見極めることです。
しかし、日本の教育は、残念ながら「記憶力=頭が良い」という図式で成り立っています。多くの情報を暗記し、テストで高得点を取ることが「優秀」だとされてきました。
企業が本当に求めているのは、「記憶力」よりも「考える力」です。なぜなら、「記憶」はパソコンやAIが代替できるからです。
この「記憶力」を伸ばそうとすればするほど、「考える力」は低下する傾向にあります。
例えば、テストで高得点を取るためには、歴史の出来事や数学の定理の「意味」を深く考える必要はありません。「大化の改新はなぜ起こったのか?」や「ピタゴラスの定理はどういう理由で生まれたのか?」を考えている暇があったら、ひたすら暗記して丸覚えした方が効率が良いからです。
極端な話、人間本来が持つ「考える」という動作を捨てれば捨てるほど、良い大学に行けるという皮肉な構図になっています。
思考停止がもたらす悲劇
この結果、何が起こるのでしょうか?
「モズのはやにえ」という言葉を聞いたことがありますか? モズという鳥は、捕まえた獲物を木の枝などに刺して蓄えておく習性があります。しかし、そのほとんどはそのまま放置されます。
なぜ取りに来ないのか?
モズは頭が悪いからではありません。実は、モズは写真を撮ったように鮮明に風景を記憶しています。しかし、その記憶はあまりに精密すぎて、落ち葉が1枚でも増えたり、風で枝の向きが変わったりすると、それが同じ場所だと認識できないのです。
つまり、「考える」ことができないのです。
生物は、思考が複雑になり高等になるほど、写真のような精密な記憶から、「抽象的」な記憶へと変化していきます。
小さな子供が駅名をすべて覚えているのは、知性が未熟なため、「興味や意義」がなくても単純に暗記できるからです。
無意識との対話を取り戻す
人間の無意識は、外部から何かを強制されると、基本的に「拒絶」するようになっています。だから、特に「興味も意義」もないことを覚え続けるのは、心にかなりの負担をかけます。
そして、「考える(確かめる)」ことなく信じた情報は、無意識は拒絶してしまうのです。
それでは、いくら「偉い先生の話」だろうと、「売れている成功本」だろうと、「カウンセラーの話」だろうと、意識で無理やり「これは正しい」と思い込もうとしているに過ぎません。
このような思考の仕方を続けていると、無意識はどんどん心を閉ざしてしまいます。
その結果、無意識の中にある**「自分の本当の夢」や「本当にやりたいこと」**を聞き出せなくなってしまうのです。そして、無意識が完全に心を閉ざしてしまうと、「鬱」などの形で体にSOSを送ってくることさえあります。
もちろん、「考える」ことだけがすべてではありません。時には、「感じる」ことの邪魔をすることもあります。
しかし、「自分で考える」ということは、人間にとって自然な行為なのです。まずはそれができないと、「感じた」としても、それをどう処理していいかわからなくなってしまいます。
誰かから意見を聞いたり、本を読んだりすることは素晴らしいことです。でも、得た情報に対して、たまには立ち止まって**「自分で考えてみる」**時間を持つこと。それが、あなたの人生をより豊かにする第一歩になるはずです。

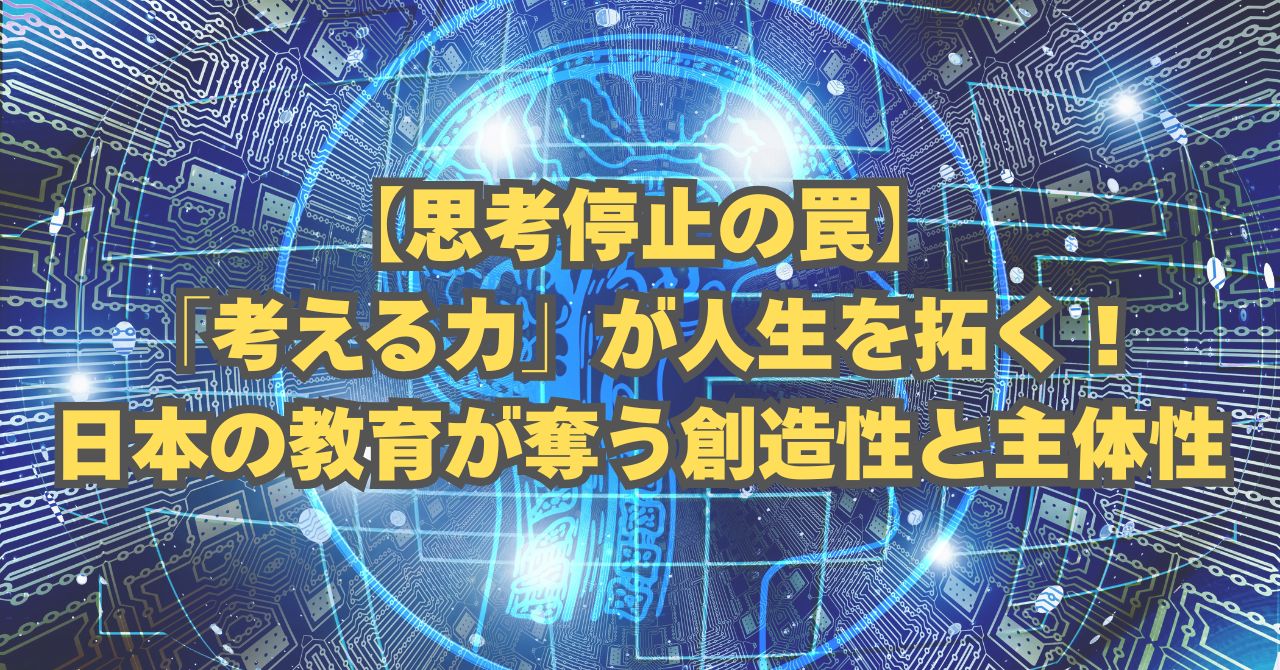
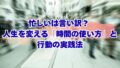

コメント